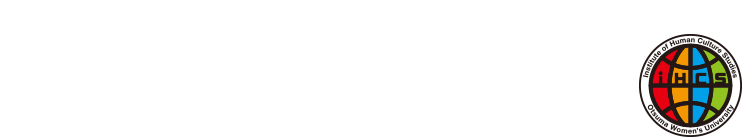No.23
『「人間」って何ですか』
メディア・リテラシーの重要性

「著者より」同書は、新宿区に拠点を置く「人間学研究会」の六十周年の成果を記念する目的で、二〇二四年に上梓した。同研究会は、「人間とは何か」について研究者と実務者が垣根を超え討議する場で、私は古くからの会員である森岡修一大妻女子大学名誉教授の誘いで入会し、毎月一回開かれる会合に参加している。
同書で会員はそれぞれ小論を執筆し、私は「プロパガンダ(Propaganda)」を取り上げた。プロパガンダは「政治宣伝」と翻訳され、「特定の政治目的を持ち、対象とする個人、集団を意図した政治目的へ導く、説得コミュニケーション行為」と定義される。戦時では敵国の邪悪性を強調し、自国の戦争目的を正当化するのが目的で、多分に「虚偽性」を帯びた情報を用いるのが特徴だ。
プロパガンダの展開は、ウクライナ戦争では「情報戦」「認知戦」と呼ばれるが、今に始まったのではない。「第一次大戦がプロパガンダの発見をもたらした」(H・ラズウエル)と指摘されるように、第一次大戦では「宣伝戦」、第二次大戦では「思想戦」、冷戦では「イデオロギー戦」「心理戦」と呼称されている。日本はアメリカを「鬼畜」、アメリカは日本を「頭が狂った猿」と、双方が相手国を下等動物に例えて敵愾心を煽ったことなど、同書で戦時プロパガンダの歴史を検証した。
プロパガンダは戦時ばかりでなく、平時でも展開される。卑近な例は兵庫県知事選におけるSNSを用いた選挙戦が挙げられる。情報は氾濫し、偏在し、欠落する。情報が、どのようなプロセスを経て、自身の手元に届いたのか。情報の送信者は何者なのか、そこに存在する意図は何かなど疑問を有して情報に接することが、プロパガンダの虚偽性を見抜く手段となる。情報社会の深化で、リテラシーを養うことの大切さがこれまで以上に求められる。
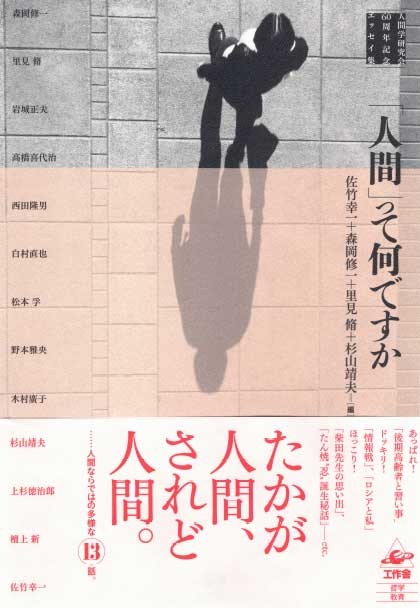
- 書名:
- 「人間」って何ですか
(工作舎)
- 編者:
- 里見脩 森岡修一 佐竹幸一 杉山靖夫
- ISBN:
- 978-4-87502-561-0
- 里見 脩(さとみ しゅう)
大妻女子大学人間生活文化研究所特別研究員、平成31年3月まで大妻女子大学文学部コミュニケーション文化学科教授、専門はメディア史。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得満期退学、学術(社会情報学)博士。主な著作『言論統制というビジネス』(新潮選書)、『新聞統合 戦時期のメディアと国家』(勁草書房)、『ニュース・エージェンシー 同盟通信社の興亡』(中公新書)、『岩波講座「帝国」日本の学知』第4巻(共著 岩波書店)