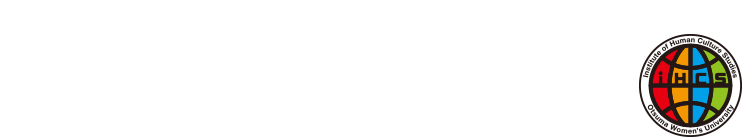No.23
『源氏物語』の読書会

この読書会の出発は、運命的な参加者との出会いです。私は大妻女子大学・短期大学の教員となった翌年に文学部国文学科1年B組のクラス担任となりました。遙か40年前のことです。当時、狭山台校での体育祭で、黄色の帽子を被った小学生に仮装した私の写真が今も残っています。
私には1年次の担任だけだったこのクラスは、なんと卒業後数十年を経る中、2~3年ごとにクラス会を途切れずに続けていて、私は退職する前年に、卒業論文製作のための元ゼミ生で北海道から上京して参加する者もいると誘われ、初めて参加しました。参加した卒業生は20数名で、私のゼミ生は8名のうち4名が参加し、盛り上がってラインを始めることになりました。その後、他の3名も加わって、在京の6名が連絡を取り合う中で、翌春に私が退職して余裕ができたことを契機として読書会を始めることになりました。
読書会の会場は、図書館4階のラーニングコモンズを借りて、土曜の午後に『和泉式部日記』を読むことから始めました。小さな作品ですが、平安時代の女性による仮名散文と和歌のエッセンスを丁寧に読むことで、学生時代の学習を思い出すことから始めました。
新型コロナウイルスの流行による中断を挟み、現在は主会場を人間生活文化研究所のセミナールームに移して、「源氏物語」の中から「宇治十帖」を読んでいます。参加メンバーは元ゼミ生以外も加わり10名になりましたが、全員平日は仕事があり、比較的集まりやすい土曜午後にしても、実施は3ヶ月に1回、実際の参加者は5~8名というのが現状です。
この「宇治十帖」は、世界遺産「源氏物語」の最終到達点で、質・量ともに充実した内容なため、読書会は予め私が作成した該当部分の概要をラインで送って予習の助けとし、当日はほぼ私が作品内容を追って話すことで時間いっぱいです。今は、2年掛かりで600頁ある文庫本3冊の1冊を読み終えた段階で、私の存命中に読み終えることを願っています。
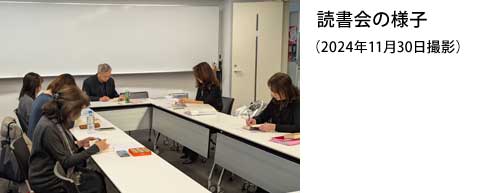
柏木 由夫(かしわぎ よしお)
大妻女子大学名誉教授(平成31年3月まで文学部教授)大妻女子大学人間生活文化研究所特別研究員。中古文学会、和歌文学会、解釈学会会員。平安時代後期の和歌文学研究が専門。昭和24年、東京生。東京教育大学卒、同大学院修士課程修了。『金葉和歌集 詞花和歌集』(「金葉和歌集」を他1名と校注を共著 新日本文学大系 岩波書店 平成元年刊、同集の改訂を他1名を加えて、岩波文庫として令和5年刊)、『平安時代後期和歌論』(単著 風間書房 平成12年刊)、『金葉和歌集 詞花和歌集』(「詞花和歌集」の校注を単著 和歌文学大系 明治書院 平成18年刊)、『大妻文庫2 詞花和歌集』(大妻本の影印翻刻 上記ゼミ生の久万田(旧姓 渋谷)文代氏の卒論に基づき、本学大学院卒の深澤瞳氏と共著 新典社 平成24年刊)、『平安和歌・物語に詠まれた日本の四季』(単著 風間書房 令和3年刊)。他にweb版の連載エッセイ(tenki.jpサプリ)「意外と知らない百人一首の世界を探求」を第17回で終了した。本学文系紀要に連載した「道命阿闍梨集注釈」の書籍化が最新の課題。