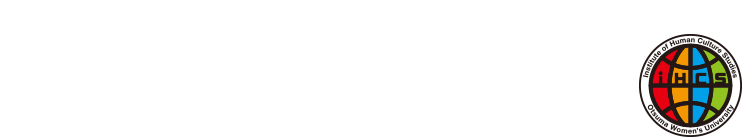No.24
高度成長期日本の経済政策

40年ほど前、高度成長期の日本経済、とくに財政金融構造や産業構造・市場構造について何本か論文を書き、一般読者向けの著書も出版しました。1970年代に入って、ドルショックやオイルショックが世界を襲い、先進諸国がいっせいにスタグフレーション(=不況とインフレの同時併存)に襲われるなか、日本経済だけは、この二つの危機を「上出来」に乗りきって5%成長を実現していました。なぜ日本だけがそうした危機に陥らなかったのか、戦後日本の経済復興とその後の発展のありかたが、1970年代以降の日本の例外的「成長」を支えたのではないか。当時は、こうした問題関心から、高度成長期日本の経済システム・経済構造や経済政策の検討を行ったのでした。
しかし、その後1980年代後半のバブル経済とその後のバブル崩壊以降、日本経済は「失われた30年」に突入します。長期のデフレと生産性上昇の停滞に直面したのです。かつて1990年代には世界のトップクラスにあった一人当たりGDPは、2024年には世界38位(IMF統計、USドルベース)まで落ち込んでいますし、債務残高の国際比較(対GDP比)では、日本は237%、スーダンに次ぐ第2位で、世界最悪の水準に達しています。政府債務の主軸である国債の残高は1100兆円、その50%以上を日本銀行が保有し、金融政策を大きく制約しています。国際的な生産や流通のネットワークを主導することもできず、情報プラットフォームを作り出すことにも成功していません。なぜ日本だけがそうした状況に陥っているのか。1970年代、80年代の「成功」と90年代以降の「失敗」は、実は表裏一体の現象といえるのではないだろうか。改めて高度成長期日本の経済政策をそうした視点から再検討してみようと考えた次第です。