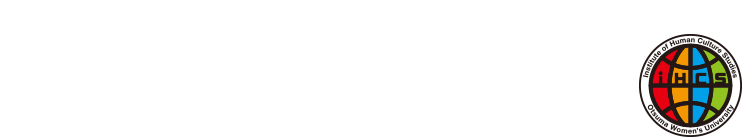No.24
就学後の読み書き⼒の基盤を育てる継承⽇本語幼児に適した⽀援⽅法の開発
- 研究代表者
柴山 真琴
家政学部ライフデザイン学科・教授
- 研究種目
- 基盤研究(B)
- 研究期間
(年度) -
2025年(令和7年)
−
2029年(令和11年)


研究の背景
グローバル化の進展により、二言語を同時習得する子どもが増えている。平日は現地校に通い、週末に日本語補習授業校(国語を中心とした授業を行う日本の在外教育施設。以下、補習校)に通う海外在住児はその代表例である。現地語と比べると接触の質量や使用の機会が十分ではない日本語(継承語)で、教科学習に必要な読み書き力をいかに育成し維持し続けるかが補習校教育の重要な課題となっている。特に現地語が日本語より優勢で家庭での日本語使用が少ない国際結婚家族の子ども(国際児)は、日本語習得上の困難さがより大きいと言われている。
筆者は、補習校小・中学部に通う独日・台日国際児を対象に、読み書き力の中でも語彙力・文法力・談話構成力等の複合的な力が必要になる書く力の形成過程を解明するために、 3つの科学研究費による共同研究(2010-13年度、2014-18年度、2019-23年度)を進めてきた。その過程で、就学後の読み書き力を下支えする日本語力の基盤(音韻意識・語彙力等を含む)が幼児期に十分に育っているのだろうかとの気づきが得られ、本課題の着想に至った。特に国際児の場合、補習校小学部入学時点で日本語力の個人差が大きいことから、就学前の幼児期に日本語力の土台をつくることの重要性が示唆された。
研究の目的と意義
就学後の読み書き力につながる幼児期のことばの力は、「萌芽的リテラシー」(Emergent Literacy:EL)と呼ばれている。本課題では、就学後の読み書き力の発達は就学前からの連続的な過程であると捉え、以下の2つを目的としている。なお、本研究では、ELを「ことば・文字に関わる諸活動への参加によって形成される読み書き力を下支えする基盤」として広義に捉えている。
【目的1】日本語を継承語として習得する幼児のEL形成過程に見られる特徴を、優勢言語の違いも視野に入れながら、補習校幼稚部に通う国際児の事例に基づいて具体的に解明すること。
【目的2】それを踏まえて、就学後の読み書き力の基盤を育てる、継承日本語幼児に適した支援方法を開発・試行すること。
継承日本語教育を必要とする子どもの増加と低年齢化への対応は、世界のどの地域にも遍在する課題であり、<子どもの発達段階-同時に習得する優勢言語との関係-日本語資源に関わる環境>の連関の中で、 継承日本語教育を検討する必要がある。2つの研究目的を達成できれば、研究蓄積の少ない継承日本語力の発達における幼児期の重要性を示す学術的知見を提供できると共に、現場の実践の改善にも寄与できることが期待される。