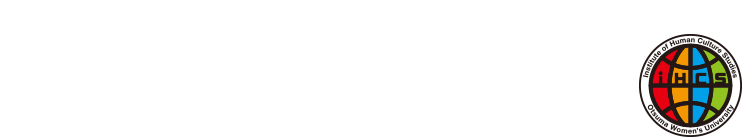No.24
談話・テクストの意味の理解に関わる構文的知識の研究
- 研究代表者
天野 みどり
文学部日本文学科 教授
- 研究種目
- 基盤研究(C)
- 研究期間
(年度) -
2025年(令和7年)
−
2029年(令和11年)


文の意味は、その文を構成する要素の意味の総和では得られず、文全体に一つの意味が慣習的に結びついていると考えられる場合があります。近年、言語学の研究分野ではこのように文全体の形と意味とが慣習的に固く結びついているものを「構文(construction)」と呼び、様々に研究されています。本研究では、こうした構文的知識が単に一文の意味の理解に関わるだけでなく、二文以上の文の連接的意味の理解にも関わることを明らかにします。
例えば次のAB二人の会話は「それが」で連接されています。A「先方へ依頼した結果はどうでしたか?」B「それが…。先方が入院してしまいまして…。」このAとBの会話の連接を理解するのに、一文の、例えば「昨日までは晴れていたのが一転して悪天候になってしまった」のような、ある状態が異なる状態に変化することを表す構文の知識も関わっていると思われます。「~のが~になった」という文の形と意味に関する知識が、「それが…、」という発話から呼び起こされ、Bが言語化しない意味、つまり〈報告するはずだったのが、先方が入院して依頼すらできなくなった〉という下線のような意味まで理解されるのです。母語話者に限らず、その言語の熟達者は、文の形と意味の結びつきに関する知識を言語使用の中で得ており、創造的な言語の産出や理解を柔軟に行っています。本研究ではこうした談話やテクストという大きな流れの中での構文の貢献を、三種の構文の実例調査により明らかにする予定です。談話・テクストのジャンル特性や場面、媒体の異なり等をも視野に入れた構文研究と言えます。
古来、日本語は英語や中国語とは異なり、文として切れそうで切れずに続く「節連鎖」の特徴があると言われてきました。「節連鎖」に限らず「文連鎖」、つまり、形としては文として切れていても意味的に従属的に次々と続く場合もあります。このような連鎖を可能にする構文的知識の考察も行う予定です。こうした考察により、言語の普遍性と日本語の個別性の一端を明らかにし、多言語社会に欠かせない言語の多様性の理解にも、日本語文法論の立場から貢献できればと願っています。