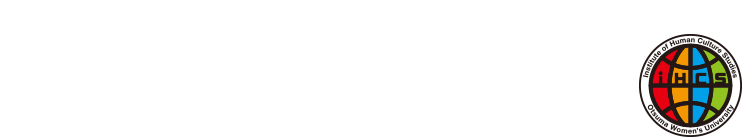No.24
意識障害のある特養入居者に対する生理的指標を用いた離床ケア評価手法の構築
- 研究代表者
井上 修一
人間関係学部人間福祉学科 教授
- 研究種目
- 基盤研究(C)
- 研究期間
(年度) -
2025年(令和7年)
−
2028年(令和10年)


特別養護老人ホーム(以下、特養)入居者の中には、意識障害の進行や身体症状の進行に伴って寝たきりになり、意思疎通が難しくなる方がいます。その方に対するケアは、援助者が、専門的判断のもとで行っていますが、本人にとっての快適さや不快さを確認することは容易ではありません。意識障害がある特養入居者へのケアを評価する場合、一般的には表情を読み取る評価方法(フェイススケール)が採用されています。施設ケアにおいて、意識障害がある特養入居者に対する支援は、表情や覚醒時間増加等で評価されていますが、支援方法の妥当性を検証するには課題が残ります。特に、意識障害があって、表情変化も乏しい特養入居者の場合は、支援の適切さを評価する基準や手法が確立していない状況にあります。
そこで、我々は唾液アミラーゼ値と心拍変動を併用してストレスを測定することとしました。唾液アミラーゼは、不快なストレッサーで数分以内に上昇し、さらに快適な状態になると下降します。測定後は、約30秒で結果が判明します。唾液から分析できる本手法は、体を傷つけることがなく、即時性、簡便性に優れ、負担が少ないメリットがあります。また、心拍変動の特徴として、本人の基準値を目安にした場合、ストレス反応時に一時的に低くなる傾向があります。そうした特性を利用し、意識障害がある特養入居者のストレス把握に唾液アミラーゼ値と心拍変動の測定を併用することとしました。
我々は、意識障害がある特養入居者のストレスを測るため、ケアの前後で唾液アミラーゼの測定を行ってきました。離床、胃ろう、食事、入浴、排泄、面会と比較した結果、有意なストレス上昇がみられたのは、「離床ケア」でした。この結果を受け、我々は、「離床ケア」の①「不安定さ」、②「体に触れられること自体の抵抗」、③「次の展開のわからなさ」、④「ストレッチャーの不快さ」の4つをストレス要因として仮定し、睡眠サイクルを踏まえて検証することしました。
ケアのなかで相手に身をゆだねることは、当然、緊張や不安を伴います。本研究の対象者は、体に触れられると体を強ばらせる傾向にあることが情報共有されていました。それが離床という、次の動作や目的が伝わりにくいケアであったからこそ、顕著に現れたと考えられます。我々は寝かせきりにしないケアをめざし、積極的に離床を促してきました。しかし、「離床ケア」が意識障害のある特養入居者にストレスを与えていたことは重要な情報でした。今回の研究によって入居者のストレス、不安を和らげる試みが検証されれば、「離床ケア」がより効果的なケアとなると考えています。