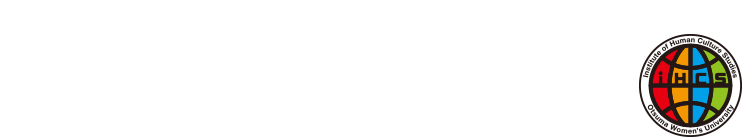No.24
日本企業の多面的対中国経済関係に関するミクロデータ計量実証分析
- 研究代表者
冨浦 英一
データサイエンス学部 教授
- 研究種目
- 基盤研究(C)
- 研究期間
(年度) -
2025年(令和7年)
−
2027年(令和9年)


世界の貿易は分断の様相を強めているが、特に米中対立の中で中国への過度の依存が問題視されるようになっている。しかし、その実態把握は容易ではない。そこで、独自調査を行って日本企業の対中依存を多面的に把握することを目指す。
国際貿易のうち、有体物(財)については、税関における通関業務を通じて収集されたデータを用いて詳細な実態把握が行われてきた。更に、Baldwin, R., Freeman, R., and Theodorakopoulos, A. (2023) “Hidden exposure: Measuring US supply chain reliance,” Brookings Papers on Economic Activity, Fall が、投入産出関係を遡ることにより米国の「隠れた」中国依存度を報告しているように、中間財貿易で複雑に絡み合った今日的な国際分業の中での対中依存度の算出も行われるようになった。
しかし、サービス貿易については、通関データのように詳細な分類での情報は国際収支統計からは得られない。Fort, T. (2023) “The changing firm and country boundaries of US manufacturing in global value chains,” Journal of Economic Perspectives 37(3), pp.31-58が米国の企業データに基づいて主張しているように、中間財貿易のデータだけではサービスの投入を伴う今日的なグローバル・バリューチェーンの実相を捉えられず、財の貿易だけでは製造の比重が下がった先進国企業のグローバリゼーションを把握することは困難になってきている。加えて、増勢を続けるデジタル・データの越境移転についても、規制を強化する国が増えているにもかかわらず、公的統計では情報が収集されていない。
このため、経済産業省企業活動基本調査と同じ企業を対象として、技術を含むサービスの貿易やデータの越境移転等に関する独自調査を実施したところで、調査結果の分析を進めている。こうした国際的にも貴重なデータ収集により、中国依存の実態を財の貿易だけでなく多面的に把握する一助となると期待している。