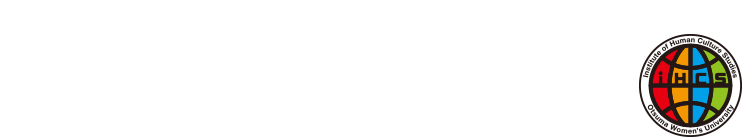No.24
タゴール仏教文学とその思想的背景―英語文学が繋ぐタゴールと近代日本仏教

インドの詩人ラビンドラナート・ゴールは仏教を通して「アジアの精神的統一」を希求したと言われる。1902年、インドを訪問した岡倉天心が夢見たものも仏教を通じてのアジア統合であった。この二人の友情を通して日本人仏教者・仏教研究者たちとタゴールの交流が展開する。
一方、タゴールはブラーフモ・サマージ(ヒンドゥー教改革派)に属し、ブラフマンへの祈りの姿勢は基本的に一生変わらなかったと言われる。タゴールの仏陀への深い尊崇の念とブラフマンへの敬虔な祈りの姿勢、この両者の関係は時に矛盾あるいは折衷的と批判されながら、議論は表層的なままで終わり、タゴールの宗教観についての研究の進展は見られなかった。
タゴールの仏陀への尊崇の念は仏教復興への熱意に燃える日本人仏教者のみならず、アジアおよび世界の仏教者たちとを結びつけ、世界思想家として評価されるタゴールの思想の中核の一つをなすのが仏教であることは疑いえない。だが、重要度に比して彼の仏教観についての研究はさほど活発なものではなかった。
この状況を鑑み、世界仏教文学史上比類のない深い大乗仏教観を示唆するChandalika(被差別カーストの少女と苦行者との物語)に着目し、その仏教的背景を日本仏教者との知的交流の中に探ってきた。なぜなら、大乗仏教を軽視した西欧の仏教学の影響下にあったインドにおいて、彼が大乗仏教の真髄を理解できた理由は彼らとの交流にあったと考えられるからである。
それは日本仏教者との直接的な人的交流に留まらない。原始仏教を重視する西欧の近代学術の潮流に抗して大乗仏教の意義を主張するために、多くの日本の仏教者・思想家が海外に向けて膨大な英文の著作を著していった。タゴールはその読書体験を通じて大乗仏教理解を深めていったのである。
今後はより重要な関係をもつ岡倉天心の仏教観および彼の傑出した仏教文学との比較考察により、タゴールの大乗仏教理解への天心の影響力の大きさについて探究していきたい。