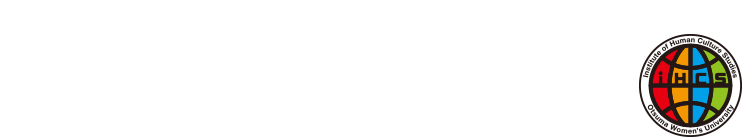No.24
元人間生活文化研究所所長 大澤清二先生
令和七年春の叙勲 瑞宝中綬章を受章

令和7年春に瑞宝中綬章をいただき、皇居で天皇陛下に謁見して、古代的な感覚とでもいうのでしょうか、日本人であることを実感しました。叙勲の理由には大学の管理運営などへの評価もあったのでしょうが、ここでは研究教育活動を点描してご挨拶といたします。
梅雨時には、ぬかるみに備えて長靴で教室に向かう、という草創期の筑波で、大学人人生が始まりました。担当していた統計学のゼミでは院生たちと深夜まで議論をし、ずいぶん冒険的な調査もしました。彼らの9割以上が大学人となり、既に定年を迎えた人もいます。筑波での10年が過ぎたころ、研究環境に魅力を感じて、大妻の研究所の発達環境研究部門(平井信義教授の後任)に移りました。爾来、アジアの子供たちの発育や生態研究に従事しました。当時この分野を選ぶ日本人は稀でした。学部の授業では統計学、大学院では生物統計学を担当しました。毎回の講義に学内外の先生たちが聴講しに来られるのには驚きました。博士課程の指導に係わり、後に6人が大学教員になりました。
海外調査は、タイや中国の雲南や新疆にはじまり、後にミャンマー、ネパールにも足をのばしました。研究資金は私学財団、トヨタ財団、文科省国際協力事業、学振のアジアアフリカ学術基盤整備事業、科研費などの支援でなんとか賄いました。外国人の調査が困難なミャンマーで政府の協力を得て、全国調査も実施できました。
今世紀にはいってからは、学術的に貴重な情報が得られる狩猟採集民の研究に取り組んでいます。長年の夢が実現して、幻の民だったタイ山地のムラブリや、アンダマン海を遊動するサロン、百年前にベトナムからメコン河畔に移動してきたブルーなどの調査をしています。
今回の受勲は、長い間研究活動を支えてくれたタイ、ミャンマー、ネパールそして日本の友人たちみんなが喜んでくれており、それがなによりも嬉しく、感謝しております。
(叙勲にあたって、研究論文などはresearchmapに整理しました。これが一苦労でした。)
大妻女子大学人間生活文化研究所特別研究員
大妻女子大学名誉教授
元大妻女子大学人間生活文化研究所所長(2009-2020)
元大妻女子大学副学長
プロフィール
日本私立大学協会・高等教育研究所客員研究員。日本発育発達学会会長(2015年~2021年)、現在名誉会員。1946年埼玉県生まれ。東京大学大学院終了後、東南アジア医療情報センター、筑波大学を経て、大妻女子大学に勤務した。同副学長(2013年~2020年)、同人間生活文化研究所所長(2009年~2020年)。同博物館長(2016年~2020年)。専門は発育発達学。1980年代より東南アジア諸民族の発育発達研究に従事、現在は狩猟採集民の調査を行っている。