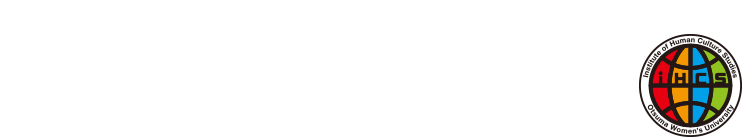No.24
子ども・若者の主体形成に関わる社会関係資本と
地域空間に関する研究

反抗期か思春期か
反抗期という言葉には大人から見て、否定的な意味で使われることが多い。『理由なき反抗』(1955年、ニコラス・レイ監督、ジェームズ・ディーン主演)に描かれたように家庭環境や学校環境の影響があっても、反抗には理由がない。この時期は身体の成長と心の成長がアンバランスで、自我の形成期の不安定さが特徴である。
チューリヒの友人宅に滞在している時に、高校生の娘さんが学校から帰ってきた時に、不機嫌の表情。親がどうしたのって聞くと「だって私、思春期だもの」と個室に飛び込みドアをバタンと閉めた。ムシャクシャする気持ちを思春期の特徴として親子で共有している。さらに驚いたのは金曜の夜、夕食後に娘さんが街の繁華街に出かけるという。チューリヒ市では金曜の夜だけ若者は夜10時まで外出していいことになっているという。
自我形成期のこの不安定な時期を思春期として社会で共有する文化を有している国と、反抗という否定的な言葉で抑えこむ国との違いはどう子ども・若者の成長に影響するのだろうか。その疑問がこの研究の発端である。
今の若者2人に1人は反抗期経験なし
本研究で20代1,000人にオンラインアンケートや本学学生に聞いた結果、約半数は反抗期がなかったと答えている。反抗することなく「いい子」で育つことが平穏で良しとされている社会の風潮も感じる。子どもの外遊びが少なくなっている今日、外遊びや地域行事に参加していた若者の方が反抗期が有るという有意な相関を見せた。
E.H. エリクソンの『アイデンティティ』が我が国で最初に翻訳出版された時は『主体性』というタイトルであった。それはガンジーの青年期の分析から、社会の改善に立ち向かう主体性は青年期にあることを突き止めたからである。
気候危機、平和の危機、民主主義の危機といわれる今日、社会の課題に立ち向かう主体性が重要となっている。それは子ども期の外遊びや思春期の社会体験を支える地域空間のあり方にあると見て本研究に取り組んでいる。